なぜ幸せを自分から壊すのか? なぜ達成を目前に失敗するのか?
それに関する興味深い海外の研究をお伝えします。
そんなセルフサボタージュしてしまう人、心理カウンセラーに役立つ内容となってます。
せっかく成長しても、成功しそうなっても、
それを自ら壊してしまうので、非常に、もったいなのです。
その原因の1つは「人は幸せよりも安定を好む」ということなのです。
この記事を読むことで、この意味が明確になります。
まずは動画からどうぞ。
⬇︎
より詳しくは以下の記事をどうぞ。カナダ人のクライアントさんの例もご紹介しています。
⬇︎
コンテンツ
セルフサボタージュとは
サボタージュ(Sabotage)は妨害、破壊という意味です。
だから、セルフサボタージュというのは、自己破壊。
自分で自分の成功や幸せなどを壊す行動ということになります。
意識的というよりは、ほぼ無意識に行っています。
自分を責める、という自責と似ています。セルフサボタージュの傾向があると、もったいないのです。
カウンセリングの現場でも、この部分も改善しないと、
せっかくいい状態に回復、成長しても、あえて悪くする傾向が出てきてしまいます。
より理解するために例をあげますね。
仕事で成功しそうになると無意識に失敗する
仕事で成功しそうになると、あえて失敗するのです。無意識に失敗する方向にいくのです。
だから、一生懸命やってるのに、なぜ大事なところで、こんなに失敗してしまうのだろう?
そう本人も周りも思っています。
その奥には、自分はダメみたいな「思い込み」があることもあります。
仕事で成功してしまうと、自分の「思い込み」とマッチしなくて、不自然なのです。
だから、失敗することで、成功しない自分でいられるのです。
恋愛が深まると、自分から別れてしまう
彼氏、彼女といい関係になったら別れるのです。
せっかくお付き合いをして、いい感じになってきてるのに、なぜか怖くなって、距離をとってしまう。
さらに、わざと嫌いな人を選ぶことで「成功や幸せ」を避ける、といういう傾向もあります。
あえて幸せになりにくような人と恋愛するのです。
この2つの例をあげましたが、私たちが思っている以上に自己破壊行動というのは多いのです。
ごく一部の人がやっているのでなく、大なり小なりみんなやっているのです。もちろん私を含めて(笑)
幸せとか成功って慣れてないのでしょう。
興味深い海外の研究結果とは
アメリカのインディアナ大学で行われたセルフサボタージュの研究があります。その結果がとても興味深いのです。
自己破壊的な行動をするのは、調子の悪い時とか、凹んでる時にするというイメージありますよね。
嫌なことがあって、気分が悪くなって、お酒を飲みまくる。過食するというように。
でも、今回の研究結果は、真逆だったのです! 1日の調子のいい時にこそ、自己破壊の行動をするというのです。
例えば、朝が強い朝方の人ほど、朝に自己破壊的な行動をするのです。夜型の人は、夜にそのような行動をするのです。

こんな感じなのです。「お〜いい感じだな〜。気分いいし、調子いいな〜。」
そんな状態が続くと、「あれ〜? 慣れてないし、違和感があるぞ〜。なんか不安になってきたぞ〜。」
だから、あえて自分からダメな状態(いつのも状態)に戻すのです。
仕事で何かに取り組んでいて、調子いい感じでやれていると….失敗したらどうしよう、と思い始めるのです。
そして、不安になって、それに耐えられなくなります。
これは1つ研究だけでなく、何度やっても同じ研究結果だったのです。信憑性があるということですね。
他には、社会的なサポートが少ない人は、セルフサボタージュしやすいという研究結果もあります。
支える人がいるのは大事ですよね。
今回ご紹介した研究ですが、とても興味深いのです。
特に「いつもと違う感じになると、不快なので元に戻そうとする」という視点です。
これより原因を探っていくので、この部分がより明確になっていくでしょう。
なぜ自分から達成や幸せを壊すのか?
価値観にマッチしてないから
自分には価値がない、幸せになれないという価値観があると、人はその通りに生きるのです。
そして、価値があるという情報を捻じ曲げたり、自分の価値が上がってきそうになると、壊すのです。
価値観については色々ありますが、浅くて考えのようなものもあります。
幼少期の頃に培った「深い価値観」というのもあります。
それは簡単には変わりません。
深い部分にアクセスするセラピーなどでないと中々変わらないです。
慣れているから
私たちはいつもの自分に慣れているのです。いつもの自分。安定した状態。
急に、あなたは素晴らしい人間だとか、成功者ですとか、受け入れられないのです。
慣れている自分を保つために、変化が起こると、セルフサボタージュするということなのです。
コントロールできるから
とってもイケメンの人とデートをしたとします。自分には、もったいないくらいイケメンで、人間性も素晴らしい。
振られるくらいなら、自分からお断りして距離をとるみたいなことです。
こうすることで「コントロール」できるわけですよね。
そのコントロールする方法が自己破壊的だというだけなのです。
失敗のリスクが上がるから
さっきとかぶってますが、自己破壊することで、失敗するのを防いでいるのです。
失敗しそうなことは、自分から放棄するということです。

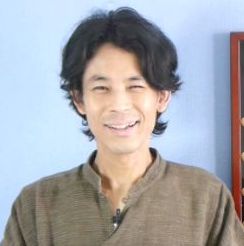

自己サボタージュの一番の理由は「抵抗」なのです
セルフサボタージュを語るのに、外せない大事な概念が「抵抗」なのです。
そもそもなぜ人は抵抗するのか? 大事な役割があるのです。
抵抗することで、安定を保てるのです。人は同じ状態でいたいという傾向が必要なのです。
新しいことをやろうとすると、危険が伴う。変化が伴う。
だから、うまくいきそうな時でも、達成しそうな時というのは変化していくことなのです。
それを食い止めるために抵抗するのは自然なことです。
その抵抗としてセルフサボタージュ的な自己破壊の行動をしてしまうということです。
この抵抗は私たちの中にある自然なサバイバルなことなのです。
変化を恐れ、安定を好む傾向が進化の過程で必要だったのです。
そう考えると自己破壊的な行動を「悪いもの」として扱わなくなります。
カウンセリングの現場でも、そうお伝えすることが改善の手助けになります。
そして、大きな変化をしないようなセッションのプロセスを促していくことも大事になります。
何か日々実践してもらうことでも、やり過ぎないのがいいのです。
いつもお伝えしている、少しずつというのが原理原則となります。
実際のクライアントさんのケースをお伝えしていきますね。
大学を卒業間近に辞めたカナダ人のクライアント
レス(30代)は大学を卒業間近で辞めたことを話してくれました。
4年間必死になってバイトで学費を稼ぎ、勉学に励んだのに。
卒業の2ヶ月前に、教授と喧嘩をしました。それまでは全く教授や他の生徒とも揉め事1つなかったのに。
なぜ急にそんなことになったのか、不思議に思いませんか?

その喧嘩を理由に、こんな学校いても意味がないと、退学してしまったのです。
彼とカウンセリングを進めていくとすぐに、これは自己サボタージュだと分かりました。
レスの加害者は「お前はだめな子だ、幸せに離れない」と何度も言ったのでした。
だから、成功や幸せが手に入りそうになると、それを何としてでも壊そうとするのです。
そうやって生きてきたのです。
彼はあるときボランティアをして、とても気分がよかったという。
しばらく、そのいい気分を味わっていたのだが、
そのうち不安になり、イライラして、いつもの依存行動に走ってしまうという。
せっかくいい気分になってるのに、なぜそれを味合わないのか、と思いますよね。
でも彼にとって「いい気分」はある意味、脅威なのです。
加害者に「幸せになれない」と言われたことがフラッシュバックしてくることもあるようでした。
そして、幸せになれない、というビリーフ(信念)が強くありました。
この傾向を彼は改善することが出来たのか?
セルフサボタージュをカウンセリングで改善
彼とのセッションでは、この自己サボタージュの傾向について取り組んでいきました。
最初は、体を感じれるようになるワークなどをやっていき、リソースを構築していきました。
「いい気分」を身体で感じることに慣れていけるようなワークもたくさんやりました。
いきなり「いい気分」というよりは、ちょっとした日常的なことで、
よかったことなどを話してもらったり、ちょっとだけ感じてもらったりしました。
自分自身の自己破壊的な行動をつかまえることもやりました。
どのような時に、どう感じて、行動しているのかということです。
認知行動療法的なアプローチも大事になります。状況、感情、感覚、行動を観察するということです。
そして、加害者が彼に言い続けた言葉にも焦点をおきました。
様々な取り組みから、彼はすべての成功を壊したわけではないという気づきもありました。
結婚、趣味の音楽、カウンセリングに来ること、学校に行くことなど、
しっかり最後まで達成したことを確認することが出来ました。
「鬱が友達で、幸せが部外者」
このように表現されたクライアントさんもおられました。
成功するスキルと力があるにも関わらず、自らそれを壊してしまうのは本当に残念で、
改善すると人生が大きくいい方向にいきます。
あなたの普段の生活で、自己破壊行動を観察してみてくださいね。
小さいことでも、これはもしかして….なんていう発見があると思います。









